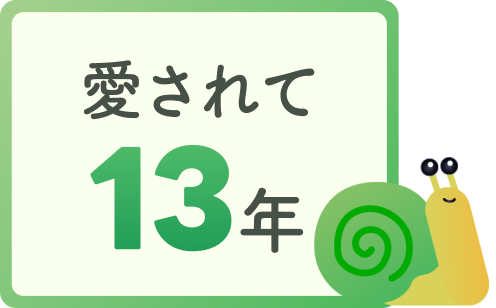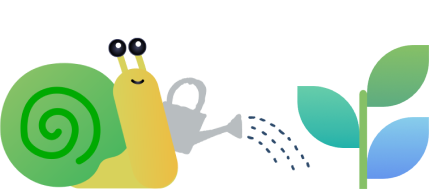当コラムでは、生成AIを使ってeラーニングの教材を制作する方法について解説してきました。前回までの解説内容で教材の構成から本編、そしてテストの作成までができますが、生成AIにはさらに活用したい使い方があります。
それは、派生的な教材の制作です。今回の解説をマスターすると、これまでリソースの問題でなかなか手が回らなかった教材を揃えられるようになるでしょう。
重要なのは、「話の流れ」
多くの生成AIは、会話形式で作業を進めていきます。そのため、「話の流れ」が重要な意味を持ちます。
ある事柄について生成AIに質問や依頼をして、生成AIがそれに回答する。その回答を踏まえてさらに要望を出すといった流れで作業を進めていくわけですが、その会話を通じて生成AIは利用者が何をしようとしているのかを学びます。
この会話の流れが生成AIによる回答の精度を高めるので、派生的な内容のeラーニング教材を生成するためには、それまでの会話の流れを踏まえて質問や依頼をするのが効果的です。
新入社員向け研修で「個人情報保護法」に特化したeラーニング教材を生成する
それでは、当コラムでこれまで解説してきた要領で、派生的なeラーニング教材を作ってみましょう。
まずは、構成の生成からです。新入社員向けコンプライアンス研修のeラーニングを制作するのにあたって、今回は以下の仕様で個人情報保護法について学ぶ教材を制作してみたいと思います。
研修の実施回数
今回は全5回とする。
直接的な目的
新入社員向けにコンプライアンス意識を高める研修を行う一環で個人情報保護法について学ぶ教材とする。
潜在的な目的
企業のリスクマネジメントの一環として、情報の持ち出しや情報漏洩などの重大な事案を防ぐ。
特に注意したい点
個人情報保護法が重く受け止めるべき法律であることをしっかり伝える。
それでは、この内容で生成AIに構成の生成を依頼してみましょう。以下のように依頼してみました。
「全5回で新入社員向けコンプライアンス研修の一環で、個人情報保護法について学べるeラーニング教材を作って。違反すると重大なことになることを伝えたい。」
この依頼に対して、以下の回答が得られました。
第1回. はじめに
企業が個人情報を適切に管理することは、法的義務であるだけでなく、企業の信頼を守るために不可欠です。本研修では、個人情報保護法の基本と、違反した際の重大なリスクについて学びます。
第2回. 個人情報保護法とは?
個人情報保護法は、個人のプライバシーを守るために定められた法律です。企業が顧客や社員の個人情報を適切に取り扱い、不正利用や漏洩を防ぐことを目的としています。
(1)個人情報の定義
個人情報とは、特定の個人を識別できる情報のことを指します。
例:
・氏名、住所、電話番号、メールアドレス
・顧客ID、社員番号
・クレジットカード情報、健康診断結果
(2)企業が守るべき基本原則
✅ 目的の明確化: 収集した個人情報は、明確に定めた目的の範囲内でのみ利用する。
✅ 適正管理: 個人情報の保存・管理を適切に行い、不正アクセスや漏洩を防ぐ。
✅ 第三者提供の制限: 本人の同意なしに個人情報を第三者へ提供しない。
第3回. 個人情報漏洩のリスクと影響
個人情報が漏洩すると、企業と個人に深刻な影響を及ぼします。
(1)企業にとってのリスク
❌ 社会的信用の失墜: 顧客や取引先からの信頼を失い、企業のイメージが悪化。
❌ 法的責任: 罰則や損害賠償請求を受ける可能性。
❌ 業務への影響: 漏洩対応に多大なコストと時間がかかる。
(2)個人にとってのリスク
❌ 経済的被害: クレジットカード情報が悪用される可能性。
❌ プライバシー侵害: 住所や電話番号が流出し、迷惑行為の標的になる。
第4回. 違反事例とその影響
過去には、多くの企業で個人情報漏洩の事例が発生し、大きな問題となりました。
✅ 事例1:大手企業の個人情報流出
・数百万件の顧客情報が外部に流出。
・企業の信用が大きく失墜し、株価が急落。
・関係者が処分を受け、多額の損害賠償を請求される。
✅ 事例2:社員のUSB紛失による情報漏洩
・業務データを入れたUSBを紛失。
・顧客情報が悪用され、被害者が発生。
・社員個人も懲戒処分を受ける。
第5回. 個人情報を守るためにすべきこと
個人情報を適切に管理するために、以下の点を徹底しましょう。
🔹 情報を持ち出さない
USBメモリや個人のPCにデータを保存しない。
🔹 適切なアクセス管理
関係者以外が情報にアクセスできないようにする。
🔹 メールの誤送信防止
送信前に宛先と内容を慎重に確認する。
🔹 不審なメールやリンクを開かない
フィッシング詐欺に注意し、怪しいメールには触れない。
かなり完成度の高い構成案が得られました。5回目の研修では「するべきこと」が例示されています。これに厚みを持たせるために、以下のように依頼してみます。
「5回目の「個人情報を守るためにすべきこと」、もっと事例を増やしたい」
この依頼に対して、以下の回答が得られました。より具体性が増して、eラーニング教材としての意義が強まったのではないでしょうか。
個人情報を適切に管理するために、以下の点を徹底しましょう。
🔹 情報を持ち出さない
USBメモリや個人のPCにデータを保存しない。
✅ 事例1:外出先でのPC紛失
営業担当者がカフェでPCを置き忘れ、顧客情報が外部に流出。 社内規則違反により懲戒処分を受ける。
🔹 適切なアクセス管理
関係者以外が情報にアクセスできないようにする。
✅ 事例2:退職者のアカウント管理不備
退職した社員のアカウントが残っており、不正アクセスが発生。 重要データが削除され、業務に大きな影響を与える。
🔹 メールの誤送信防止
送信前に宛先と内容を慎重に確認する。
✅ 事例3:誤送信による個人情報漏洩
顧客リストを誤った宛先に送信し、情報が第三者へ流出。 会社が公式に謝罪し、信頼回復に時間を要する。
🔹 不審なメールやリンクを開かない
フィッシング詐欺に注意し、怪しいメールには触れない。
✅ 事例4:フィッシング詐欺の被害
社員が偽メールのリンクをクリックし、社内システムに不正アクセスが発生。 顧客情報が流出し、会社に多額の賠償責任が発生。
この記事のまとめ
・すでにあるeラーニング教材から、派生したテーマで教材を制作できる
・深堀り質問を繰り返し、教材コンテンツの精度・価値を高めていく
#生成AIと教材制作
7 件の記事
- 【生成AIと教材制作vol.1】ご存じですか?eラーニングの教材は生成AIで簡単に作成できます
- 【生成AIと教材制作vol.2】eラーニングの教材制作に生成AIを活用するための基礎知識
- 【生成AIと教材制作vol.3】生成AIにeラーニング教材の構成を作らせてみよう
- 【生成AIと教材制作vol.4】生成AIによるeラーニング教材制作のファクトチェック、意見の多様化
- 【生成AIと教材制作vol.5】構成案からeラーニング教材の内容を肉付けする
- 【生成AIと教材制作vol.6】学習到達度をチェックするテストの作成も生成AIにお任せ
- 【生成AIと教材制作vol.7】派生的な内容のeラーニング教材制作こそ生成AIの真価が発揮される