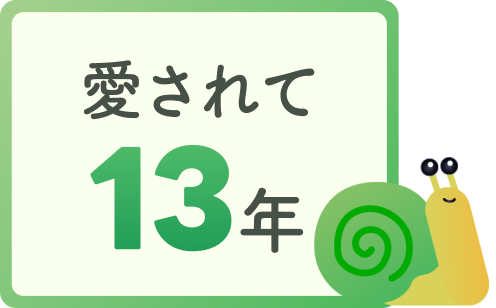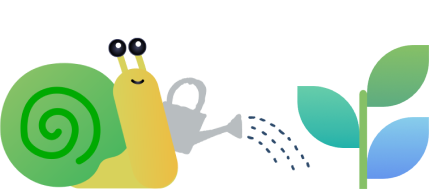生成AIを活用してeラーニングの教材を制作するのにあたって、重要なのが内容の検証です。
ネット上から情報を集め、それをまとめたり整理することに長けているのは生成AIに共通する特徴ですが、それを検証して正しいのかどうかを判断することは苦手な部分があり、間違って情報をもとにコンテンツを生成してしまう可能性があります。
eラーニング教材に間違いが含まれていると、教育内容も間違ったものになってしまいます。
今回は生成AIによるeラーニング教材制作において内容の検証をする重要性や方法について解説します。すでに前回までに新入社員向けの「コンプライアンス研修」について生成AIで構成案を生成しているので、そこまでのプロセスについてはバックナンバーをお読みください。
意外に難しい、生成AIのファクトチェック
生成AIが出力したコンテンツについては、その真贋を見極めることが当初から課題になってきました。
ネット上の情報がすべて正しいとはいえず、影響力のあるサイトだからといってすべてが事実とは限りません。そういった情報を参照して生成AIはコンテンツを作成するため、どうしても意図しない誤りが含まれる可能性が残ります。
利用者の指摘によって「この情報は間違っている」と判断すると以後は同じ間違いをしなくなりますが、再び誤った情報を鵜呑みにしてしまう可能性も十分に考えられます。
そのため、生成AIが生成したコンテンツは、検索エンジンで調べるなど人間の手でファクトチェックをする必要があります。
生成AIにファクトチェックをさせてみる
少々逆説的ではありますが、ファクトチェックにも生成AIを利用できます。質問の仕方によって異なる考え方を示してくれるので、生成AIの回答について曖昧さや疑問が残るようなことについては生成AIに聞いてみましょう。
たとえば、このコラムでは企業のコンプライアンス研修を題材としているので、ファクトチェックも兼ねて以下のような質問をしてみました。
「企業のコンプライアンスについて、少々のことであれば話し合いで解決するべき?」
それでは、生成AIの回答を見てみましょう。
企業のコンプライアンス(法令遵守)に関する問題は、その重大性や影響範囲によって対応方法が異なります。
話し合いで解決すべきケース
1.軽微なルール違反や誤解
・例えば、社内ルールの解釈の違い、小さな手続きミスなどは、まず話し合いで是正するのが適切です。
・社員が故意でなくミスをした場合、教育や指導で再発防止を図ることが重要です。
2.グレーゾーンの問題
・法律違反ではないが、倫理的に問題があるケース(例:取引先への過度な接待、社内の不透明な意思決定)。
・関係者間で透明性を持った議論を行い、ルールの明確化を図るべきです。
話し合いだけではすませるべきでないケース
1. 法令違反や重大な不正行為
例:粉飾決算、贈収賄、ハラスメント、データ改ざんなど。
これらは社内処理だけで済ませると、企業としての信用を失い、法的責任を問われる可能性があります。
内部通報制度の活用や、必要に応じて外部の専門機関(弁護士・監査法人など)と連携するべきです。
2.再発の可能性が高いケース
・例えば、過去に同じ問題が繰り返されている場合や、企業文化として根付いている場合。
・話し合いだけではなく、明確な規則の策定や社内教育、管理体制の見直しが必要です。
結論
「少々のこと」であれば、まず話し合いで解決を試みるのは良いですが、法令違反や重大なリスクが伴う場合は、適切な措置を講じるべきです。企業の信頼を守るためには、透明性のある対応と予防策が不可欠です。
話し合いで解決すべきケースと、そうでないケースを分けて2つの方向から回答が得られました。コンプライアンス違反と疑われるケースは一律ではなく、おそらくこの2つに分けられるでしょう。該当する事案がこのどちらに近いのかによって対応が分かれ、それぞれの対応はこうするべきという方向性が示されています。
ファクトチェックの一環で、このように敢えて違う方向からの質問をしてみると、より教材コンテンツの厚みが増すと思います。
異なる考え方を生成AIに模索させてみる
ファクトチェックは事実に反した内容になっていないかをイエスかノーで判断する作業ですが、「どちらともいえない」という部分に光を当てると、教材の内容をより多様なものにすることができます。
企業のコンプライアンスについて、もっと多様な意見を生成AIに質問してみました。
「コンプライアンスは多様な意見があるので、これ以外の意見はある?」
端的に言えば、現状で出ているアイディア以外にもっと他のアイディアはないかと尋ねました。
この質問に対する答えが、こちらです。
確かに、コンプライアンスにはさまざまな視点や解釈があります。以下のような考え方もあります。
1. 企業の視点:リスク管理としてのコンプライアンス
・コンプライアンスは「法律を守ること」だけではなく、「企業のリスクを減らす手段」とも考えられる。
・コンプライアンス違反が発生すると、企業のブランド価値が下がり、取引先や顧客の信頼を失うリスクがある。
・企業ごとにリスクの種類が異なるため、業界や企業文化に応じたルールが必要。
2. 個人の視点:キャリアを守るためのコンプライアンス
・コンプライアンス違反は、従業員個人のキャリアにも影響を及ぼす。
・不正やハラスメントに関与すると、懲戒処分や最悪の場合は解雇、訴訟リスクもある。
・「言われた通りにやっていた」では責任を回避できない場合もあるため、自分で考え、判断する力が求められる。
3. 社会の視点:企業の社会的責任(CSR)との関係
・コンプライアンスは「企業が法律を守ること」にとどまらず、「社会全体に対して責任を果たすこと」でもある。
・SDGsやESG(環境・社会・ガバナンス)といった概念とも密接に関わる。
・例えば、環境問題への対応やダイバーシティ推進も、広義のコンプライアンスに含まれる。
4. 海外の視点:文化や国による違い
・海外では、コンプライアンスの範囲や重要性が国によって異なる。
・例えば、欧州では個人情報保護(GDPR)が厳しく、米国では企業の透明性や内部告発制度が重視される。
・日本企業が海外でビジネスをする場合、現地のコンプライアンス基準を理解し、適応する必要がある。
5. 倫理の視点:ルールに書かれていない「正しい行動」
・コンプライアンスは「ルールだから守る」のではなく、「社会的に正しい行動をする」という考え方もある。
・例えば、法律に違反していなくても、消費者を欺くような広告や、従業員を過剰に働かせることは、倫理的に問題視される。
・企業は、「ルールを守る」だけでなく、「社会の信頼を得る行動」を取ることが求められる。
ここで筆者は、海外との違いという新しい視点(下線部分)に着目しました。これまでの回答にはなかった要素です。もし新入社員研修をする企業がグローバル企業、海外に拠点のある企業であれば、日本と海外の視点の違いに着目することは重要かもしれません。
そこでさらに、日本と海外の違いについて質問してみました。
「海外の視点が面白いね。日本と海外とでコンプライアンス意識の違いを伝えるとしたら、どんな内容がいい?」
これに対する回答が、こちらです。
1.日本と海外のコンプライアンスの基本的な違い
コンプライアンスの考え方
日本:「ルールを守ること」が中心
海外:「倫理的に正しい行動をすること」も重要
法令順守の意識
日本:企業として遵守するのが前提
海外:個人レベルでも責任が問われる
内部告発(ホイッスルブロウイング)
日本:内部告発を避ける傾向(事を荒立てない文化)
海外:内部告発を奨励し、保護制度が整備されている
ハラスメント対策
日本:指摘しづらい雰囲気がある
海外:些細な言動でも問題視され、厳しく対処
情報管理の意識
日本:企業内ルールを重視
海外:法的リスクが大きいため厳格に管理
CSR(企業の社会的責任)
日本:コンプライアンスとは別に考える傾向
海外:環境・人権・ガバナンスもコンプライアンスの一部
✅ ポイント
日本では「ルールを守ること」が中心になりがちだが、海外では「倫理的に正しいか」が問われる場面が多い。
2. 具体的な違いをケーススタディで学ぶ
ケース1:内部告発の扱い
シナリオ:
・日本企業で、上司が経費を私的に利用しているのを目撃。しかし、部下は「上司に逆らうと職場での立場が悪くなる」と思い、黙認する。
・一方、米国企業では、内部通報制度(ホイッスルブロウイング制度)が整備されており、通報した社員は法律で保護される。
👉 ポイント:
・日本: 内部告発は「裏切り」と見られることもあり、ためらう傾向。
・海外: 不正を見逃さない文化があり、内部告発が奨励される。
✅ 対策: 日本でも内部通報制度を強化し、「通報は企業の成長にとって必要なもの」と理解を促す。
ケース2:ハラスメントの基準
シナリオ:
・日本企業では、上司が部下に「君、最近やる気ある? もっと頑張らないとダメだよ」と言う。
・部下は多少プレッシャーを感じるが、特に問題にはならない。
・しかし、欧米の企業では、「これは精神的な圧力(パワハラ)にあたる可能性がある」として問題視される。
👉 ポイント:
・日本: ある程度の厳しい指導は許容される文化がある。
・海外: 「相手がどう感じたか」が重要で、些細な言動でもハラスメントとみなされることがある。
✅ 対策: グローバルに働くなら、「自分の意図」ではなく「相手の受け取り方」に配慮することが大切。
ケース3:情報管理とプライバシー保護
シナリオ:
・日本企業の営業担当が、顧客リスト(名前・連絡先)をExcelにまとめて社内で回覧。
・これは日本では普通の業務だが、EUのGDPR(一般データ保護規則)では、顧客の同意なしに個人情報を共有することは違法となる可能性がある。
👉 ポイント:
・日本: 社内での情報共有は比較的自由に行われる。
・海外: 個人情報保護が厳しく、扱いを誤ると高額な罰金のリスクがある(EUのGDPRでは最大で年間売上の4%の罰金)。
✅ 対策: 日本企業もグローバル基準に対応し、情報管理のルールを厳格化する必要がある。
3. 日本企業が学ぶべき海外のコンプライアンス意識
✅ 1. コンプライアンスは「ルールを守る」だけでなく、「倫理的に正しい行動」を考えることも重要
✅ 2. 内部告発(ホイッスルブロウイング)を企業の成長のための仕組みとして整備する
✅ 3. ハラスメントは「相手がどう感じるか」が重要。海外基準を意識する
✅ 4. 情報管理・個人情報保護のルールを国際基準で考える
かなり完成度の高い回答が得られました。
この記事のまとめ
・ファクトチェックは、生成AIの大きな課題
・生成AI自身に質問を掘り下げるなどの会話を通じてファクトチェックさせることもできる
・同じ視点だけではなく多様な視点からの意見を求めることもできる
#生成AIと教材制作
7 件の記事
- 【生成AIと教材制作vol.1】ご存じですか?eラーニングの教材は生成AIで簡単に作成できます
- 【生成AIと教材制作vol.2】eラーニングの教材制作に生成AIを活用するための基礎知識
- 【生成AIと教材制作vol.3】生成AIにeラーニング教材の構成を作らせてみよう
- 【生成AIと教材制作vol.4】生成AIによるeラーニング教材制作のファクトチェック、意見の多様化
- 【生成AIと教材制作vol.5】構成案からeラーニング教材の内容を肉付けする
- 【生成AIと教材制作vol.6】学習到達度をチェックするテストの作成も生成AIにお任せ
- 【生成AIと教材制作vol.7】派生的な内容のeラーニング教材制作こそ生成AIの真価が発揮される